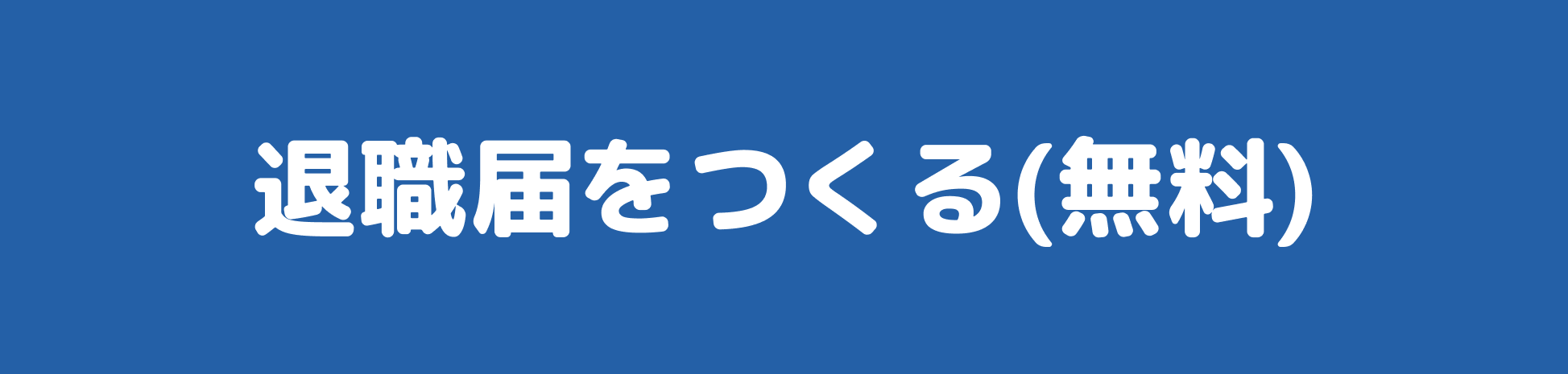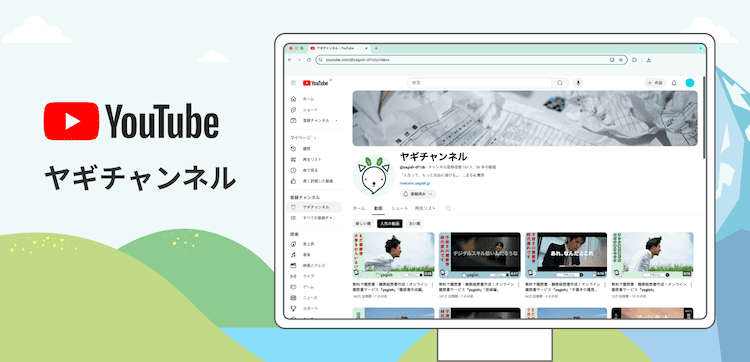2025.05.23
新卒で「辞めたい」は甘え?退職すべきかどうかの判断ポイントや注意点を解説
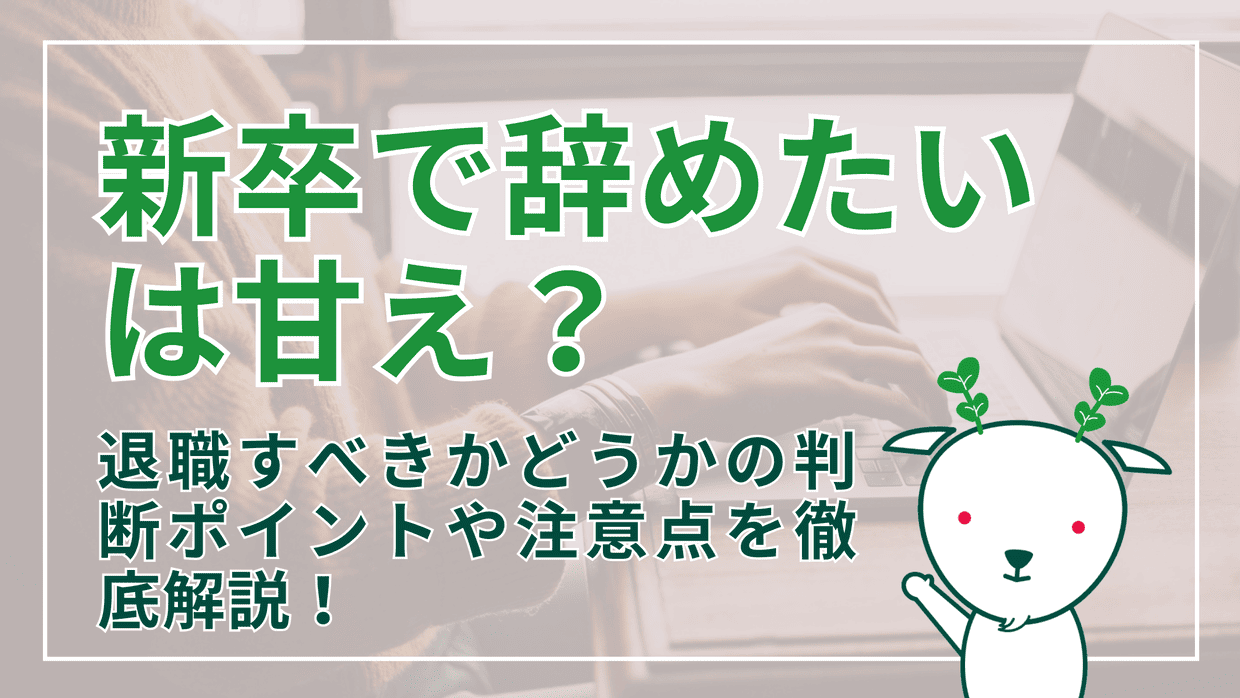
「新卒で入った会社だけど、上司と合わない」
「辞めたいけど、それって『甘え』なんじゃないか…」
新卒で入社した会社を辞めたくなることは珍しくありません。しかし、様々な悩みや不安、そして「本当に辞めるべきか?」という疑問がついてまわります。
そこで今回は
- 辞めるか否か判断のチェックポイント
- 新卒で退職したときのリスク
- 実際に新卒で退職した人の体験談
以上の要素を徹底解説いたします。この記事の内容を、ぜひ今後の判断に役立ててください。
▼無料で作成、PDFも受け取れる!オンライン履歴書Yagish▼
新卒が仕事を辞めたくなる本当の理由とは?

新卒入社後、多くの若手社会人が「辞めたい」と感じる瞬間に直面します。単なる「甘え」ではない、辞めたくなる本当の理由を掘り下げていきましょう。
自分に合わない業務内容に悩む
新卒入社後、想像していた仕事内容と現実のギャップに苦しむケースは非常に多いものです。就職活動時の企業説明会やパンフレットで描かれた華やかな仕事像と、実際の業務内容の間には大きな隔たりがあることがよくあります。
特に、「自分の強みや専門知識が全く活かせない」「学生時代に学んだことと全く違う分野の仕事を任された」といった状況は、モチベーションの低下を招きやすいものです。
また、配属された部署や担当業務が自分の適性や価値観と合わないと感じると、日々の業務がストレスになりがちです。
職場の人間関係にストレスを感じる
新社会人にとって、職場の人間関係は離職を考える大きな要因の一つです。学生時代の友人関係とは異なり、職場では様々な年齢層や価値観を持つ人々と協働する必要があります。
上司とのコミュニケーションがうまくいかない、指導方法が厳しすぎる、または明確な指示がなく放置されるといった状況は、新卒社員にとって大きなストレス源となります。
また、職場の雰囲気や企業文化が自分に合わないと感じることも少なくありません。
労働環境・条件に不満がある
実際の労働条件が入社前の説明と大きく異なる場合、新卒社員の不満は高まります。
慢性的な残業や休日出勤が当たり前の職場環境では、プライベートの時間が確保できず、疲労が蓄積していきます。
また、給与や待遇面での不満も無視できません。同業他社と比較して低い給与水準、昇給やキャリアパスの見通しが不透明といった状況は、将来への不安を生み出します。
リモートワークの可否やフレックスタイム制度の有無など、働き方の柔軟性に関する条件も、今の若手社員にとっては重要な判断材料です。
「すぐ辞めるのは甘え?」という声にどう向き合うか

新卒として入社したばかりで「辞めたい」と感じると、周囲から「それは甘えではないか」という声が聞こえてくることがあります。
しかし、「辞めるのは甘え」という言葉をそのまま受け入れる必要はありません。
よく言われる「新卒は最低3年は働くべき」という考え方は、高度経済成長期の終身雇用を前提とした時代の名残です。当時は企業が社員教育に時間とコストをかけ、3年程度で一人前になることを期待していました。
しかし現代では、雇用環境や働き方が大きく変化しています。終身雇用は崩壊し、転職が一般的になりつつある中で、この古い価値観だけにとらわれる必要はないでしょう。
「仕事が思ったより大変」「朝早く起きるのがつらい」などの理由だけで辞めることは、社会人としての耐性を身につける機会を逃してしまう可能性があります。これは「甘え」と評価される場合もあるでしょう。
一方で、過酷な労働環境やハラスメント、自分の価値観と大きく異なる企業文化など、健康や人格を損なう恐れがある状況からの撤退は「自己防衛」です。これを甘えと混同すべきではありません。
甘えと言われることを恐れず、自分の状況を客観的に分析し、自分の人生に責任を持った決断をすることが、社会人としての真の成熟と言えるのではないでしょうか。
職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き
新卒が会社を辞めた方がいいと判断できるケース

新卒で入社したばかりでありながら「辞めたい」と考えることは決して珍しいことではありません。ここでは、新卒社員が会社を辞めることを前向きに検討すべき状況について解説します。
体調やメンタルに悪影響が出ているとき
最も優先すべきは自分の健康です。仕事によって心身の健康が著しく損なわれているなら、それは退職を検討すべき重大なサインと言えます。
具体的には、以下のような症状が続く場合は要注意です
- 慢性的な不眠や睡眠障害
- 出社前の強い不安感や吐き気
- 休日や休暇を取っても回復しない疲労感
- 食欲不振または過食
- 抑うつ感や無気力感が続く
パワハラ・モラハラの被害に遭っている
職場におけるハラスメントは、法律で禁止されている明確な退職理由となります。
以下のような行為が継続的に行われている場合、それはハラスメントに該当する可能性が高いです:
- 上司や先輩からの過度な叱責や罵倒
- 能力や経験に見合わない無理難題の要求
- 意図的な仕事の機会剥奪や孤立化
- プライベートへの不当な干渉や侵害
- 身体的な暴力や脅し
ハラスメントに遭っている場合、まずは社内の相談窓口や人事部門に報告することが望ましいですが、それでも状況が改善されない、あるいは報復を恐れて相談できない状況であれば、退職を選択することは自己防衛として正当です。
会社都合退職とは何?自己都合退職との違い、メリットデメリット、失業保険や退職金も解説!
どうしても将来性が見いだせないとき
入社してみたものの、想像していた仕事内容や業界の実態が大きく異なり、このまま続けても自分のキャリア形成に寄与しないと感じる場合があります。
ただし、この判断は慎重に行う必要があります。新卒1年目では業務の全体像が見えていなかったり、自分の適性が十分に発揮できていなかったりする可能性もあるためです。
違法行為や倫理的に問題のある業務を強いられる場合
会社から違法行為や倫理的に問題のある業務を要求されるケースも、即座に退職を検討すべき状況です。
例えば
- 虚偽の報告書や経理処理の作成を指示される
- 顧客に対する詐欺的な販売手法の強要
- 安全基準を無視した業務遂行の要請
- 労働法規違反(サービス残業の強制など)
このような状況に直面した場合、自分自身の法的リスクを回避するためにも、また将来のキャリアに傷をつけないためにも、会社との関係を見直すべきです。
在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など
退職前に考えておくべきポイント

新卒で入社した会社を辞めることは大きな決断です。感情的になりがちな状況だからこそ、以下のポイントを客観的に検討してみましょう。
誰かに相談できる環境はあるか?
退職を考える前に、まずは信頼できる人に相談することが重要です。一人で抱え込むと、客観的な判断ができなくなりがちです。
社内であれば、直属の上司以外にも、人事部や先輩社員、メンターなどに相談できる可能性があります。特に新卒採用に力を入れている企業では、新入社員向けの相談窓口が設けられていることも多いでしょう。
自分の適性に合った仕事なのか?
現在の仕事と自分の適性がマッチしているかを客観的に分析することが大切です。単に「やりたくない」という感情だけではなく、自分のスキルや価値観、興味関心と現在の業務内容を照らし合わせてみましょう。
例えば、論理的思考を活かしたい人が感覚的な判断を求められる仕事に就いている場合や、人と接することが好きな人がデスクワークばかりの環境にいる場合など、明らかなミスマッチがある可能性があります。
また、現在の仕事が自分の長期的なキャリアプランにどう位置づけられるかも考慮すべきポイントです。
転職先が見つかる見込みはあるか?
退職を決断する前に、転職市場における自分の市場価値を冷静に分析してみましょう。新卒入社から短期間で退職する場合、次の就職先を見つけるハードルが高くなる可能性があります。
現在の就職市場の動向、自分の業界での需要、持っているスキルや資格などを踏まえて、どの程度の期間で次の仕事が見つかるか、見積もっておくことが重要です。
転職エージェントに登録して市場価値を確認したり、求人情報を定期的にチェックしたりすることで、より具体的な見通しを立てることができます。
>20代で転職すべきか迷ったら考えるべき4つのこと|転職すべきか考える時の基準と2人の実際の体験談
健康面に深刻な問題が出ていないか?
仕事のストレスが原因で健康に支障が出ている場合は、退職を真剣に検討すべきサインかもしれません。身体的な症状(慢性的な頭痛、胃腸の不調、不眠など)やメンタル面の変化(うつ状態、不安障害、パニック発作など)に注意を払いましょう。
医師やカウンセラーなどの専門家に相談し、客観的な診断を受けることも重要です。産業医がいる企業であれば、まずは産業医に相談することも一つの選択肢です。
感情だけで判断していないか?
「今日は特にきつかった」「上司に怒られた」など、一時的な感情で退職を考えていないか、冷静になって判断することが大切です。
感情を整理するために、仕事の良い点・悪い点をリストアップしたり、現在の環境で改善できる点と改善できない点を区別したりすることも効果的です。また、1週間や1ヶ月など期限を決めて様子を見る方法も、冷静な判断を助けます。
【2025年最新】転職面接で確実に聞かれる質問と回答例|転職者の状況別対策も紹介
辞めないことによるメリットとは?

新卒で入社した会社を辞めたいと思う気持ちは理解できますが、踏みとどまることにも様々なメリットがあります。ここでは、辞めずに頑張り続けることで得られるメリットについて詳しく解説します。
スキルが着実に身につく
入社してすぐは誰でも未熟で、業務に慣れるまでに時間がかかるものです。しかし、辛抱強く継続することで、着実にスキルアップを図ることができます。
ビジネスマナーや業界知識、専門スキルなど、社会人として必要な基礎能力は最初の1〜2年で大きく成長します。特に以下のようなスキルは、継続して働くことでこそ身につくものです。
- 業界特有の専門知識やノウハウ
- ビジネス文書の作成能力
- 社内外でのコミュニケーション力
- プロジェクト管理能力
入社1年目は「分からないことだらけ」という状態から始まりますが、2年目、3年目と経験を積むことで、自信を持って業務に取り組めるようになります。この成長過程は、どの会社に行っても最初は避けられないものです。
自信や実績につながる可能性がある
困難を乗り越えることで得られる自信は、キャリア形成において非常に大きな財産となります。
特に新卒1〜3年目は急成長する時期です。この時期に以下のような経験を積むことができます
- 小さな成功体験の積み重ね
- 上司や先輩からの信頼獲得
- 責任ある業務を任される機会の増加
- 自分の強みや適性の発見
また、一定期間同じ会社で働くことで、「〇〇社で3年間営業として年間目標を達成し続けた」「プロジェクトを成功に導いた」など、具体的な実績を履歴書に記載できるようになります。これは将来のキャリアにおいても大きな武器となります。
一般事務・事務職の志望動機の書き方・例文を徹底解説!転職や未経験の方必見
無料で簡単に履歴書作成する方法
Yagishは履歴書をオンラインで無料で作成、PDF保存までできる非常に便利なサイトです。
PCでもスマホでも、オンラインで利用できる豊富なテンプレート(志望動機例文付き)があります。
多くのテンプレートがあり、
全て無料で利用することができます。
志望動機の例文もあり、とても簡単に履歴書が作れます。
ぜひ一度試してみてくださいね。
>より簡単に履歴書が作れる!Yagish履歴書を見てみる♪(公式サイトへ)
新卒が辞めることで生じるリスクと注意点

新卒として入社した会社を早期に退職する決断は、将来のキャリアに様々な影響をもたらす可能性があります。この章では、新卒が会社を辞めることで生じる可能性のあるリスクや注意点について詳しく解説します。
転職市場で「中途」扱いになる
新卒で入社した会社を数カ月〜1年程度で退職すると、次の就職活動では「第二新卒」または「中途採用」としての扱いになります。
まず、応募できる求人の幅が変わります。多くの大手企業や人気企業は、新卒採用に力を入れており、中途採用枠は限られていることが少なくありません。
また、採用基準も変わります。新卒採用では「ポテンシャル」が重視される傾向がありますが、中途採用では即戦力としての「スキル」や「経験」が問われます。
さらに、給与条件も新卒採用と中途採用では異なることが多いです。
中途採用面接でよくある質問40選と回答例文|服装やマナー、面接の流れも。2025年1月29日
継続力に疑問を持たれる可能性がある
新卒入社後すぐに退職すると、採用担当者から「継続力がない」「困難に直面するとすぐに逃げ出す」といった印象を持たれるリスクがあります。
退職理由について面接で質問されることは確実と言えます。「会社と自分の価値観が合わなかった」「期待していた仕事内容と違った」といった一般的な理由は、採用担当者にとっては「この人は自社でも同じことを言って辞めるのではないか」という懸念材料になり得ます。
タイミング次第で賞与や失業手当を失う
退職のタイミングによっては、経済的な不利益を被る可能性があります。多くの企業では賞与(ボーナス)の支給対象者を「支給日に在籍している社員」と定めています。
また、失業保険(雇用保険の失業等給付)を受給するためには、原則として「雇用保険の被保険者期間が離職前2年間に通算して12か月以上あること」という条件があります。
新卒で辞めた人の体験談5選(ケース別)

新卒入社後に退職を決断した人々の実体験は、同じ悩みを抱える方にとって参考になるケースが多くあります。ここでは様々な状況で会社を辞めた5人の体験談をご紹介します。
ブラック企業で残業月100時間を経験し3ヶ月で退職したAさん
Aさん(27歳・男性)は、大手広告代理店の子会社に新卒入社しました。入社前はクリエイティブな仕事に携われることを期待していましたが、実態は月100時間を超える残業と、休日出勤が当たり前の環境でした。
「入社してすぐに先輩から『ここは辞めるまで帰れないよ』と言われ、実際その通りでした。朝8時に出社して、終電で帰るのが日常。土日も出社が基本でした。3ヶ月目で体重が10kg減少し、常に頭痛がする状態になったんです」とAさんは語ります。
退職を決意した理由は、明らかな健康被害が出始めたことと、その労働環境に見合った成長やスキルアップが得られないと判断したからです。
退職後は3ヶ月の療養期間を経て、ワークライフバランスを重視する外資系企業に転職し、現在は適切な労働環境で働いています。
やりたい仕事と違った現実に半年で転職を決めたBさん
Bさん(25歳・女性)は、憧れていた出版社に入社しましたが、配属されたのは営業部門。編集職を希望していましたが、「まずは営業で会社の基礎を学んでから」と言われ、営業職として働き始めました。
「毎日書店を回り、返品処理や棚卸し作業が中心の仕事で、本を作る喜びとは程遠い日々でした。上司に編集部への異動希望を伝えても『最低3年は営業で実績を積まないと難しい』と言われ、このまま続けるべきか悩みました」とBさんは語ります
半年間葛藤した末、Bさんは退職を決意。その後、Web媒体の編集者として転職し、現在は本来やりたかった編集の仕事に携わっています。
パワハラ上司との関係で精神疾患を発症し1年で退職したCさん
Cさん(26歳・男性)は、地方の製造業に新卒入社。真面目に仕事に取り組んでいましたが、直属の上司からの度重なる叱責と過度な要求に悩まされました。
「些細なミスを全社員の前で大声で叱られたり、終業後に個室に呼ばれて1時間以上説教されることが日常でした。他の新入社員と比較され、『お前は使えない』と言われ続け、次第に出社が怖くなりました」とCさんは語ります。
入社8ヶ月目に不眠と動悸が酷くなり、病院で適応障害と診断されました。産業医との面談後、人事部に状況を説明しましたが、「新人のうちは厳しく指導されるのは当たり前」という回答で、配置転換などの対応はありませんでした。
1年経ったタイミングで退職を決意し、3ヶ月の休養後、社風を重視して選んだ中小企業に転職。現在は働きやすい環境で、徐々に自信を取り戻しているといいます。

成長機会が少ない環境から2年で転職し年収アップを実現したDさん
Dさん(28歳・女性)は、地元の安定した金融機関に就職しました。確かに働く環境は整っていましたが、入社2年目になっても単調な事務作業が中心で、専門知識を深める機会が少ないことに不満を感じていました。
「終身雇用を前提とした職場で、若手の意見は取り入れられず、昔ながらのやり方を踏襲することが求められました。このまま10年働いても、スキルアップできる見込みが薄いと感じました」とDさんは語ります。
将来のキャリアについて考えた結果、2年のタイミングで転職活動を開始。新卒時の就活よりも自分の適性や希望を明確にできたため、フィンテック企業への転職に成功しました。結果として年収も20%アップし、専門性を高められる環境を手に入れました。
業界・職種を完全に変更し、1.5年で起業への道を選んだEさん
Eさん(29歳・男性)は、大手メーカーの技術職として入社しましたが、組織の意思決定の遅さやイノベーションへの消極的な姿勢に違和感を覚えていました。
「新しいアイデアを提案しても『前例がない』という理由で却下されることが多く、創造性を発揮できる場が少ないと感じていました。また、キャリアパスが決まっていて、30代、40代の先輩の働き方を見ても自分の理想とは違うと思ったんです」とEさんは語ります
入社1年半で退職を決意したEさんは、IT業界のスタートアップに転職。そこでWeb開発のスキルを身につけながら自分のサービスを副業で開発し、現在はその事業を本業として独立起業しています。
いっぽうで「大企業で学んだ体系的な考え方や品質管理の知識は、起業後も非常に役立っています。辞めたことを後悔したことはありません。むしろ早く動いたからこそ、若いうちに挑戦できたと思っている」とも考えているようです。
よくある質問

親に反対されていますが、それでも辞めるべきでしょうか?
親が反対する理由は、あなたの将来を心配してのことかもしれません。まずは親の意見に耳を傾け、なぜ反対しているのかを理解することが大切です。その上で、自分の状況や気持ち、将来のビジョンを冷静に説明してみましょう。
ただし、メンタルヘルスの悪化や深刻なハラスメントなど、健康に関わる問題がある場合は、親の理解を得ることも重要ですが、最終的には自分の心身の健康を最優先に考えるべきです。
退職届の書き方や退職の伝え方で気をつけるべきことは?
退職届は簡潔に書くのがポイントです。「一身上の都合により」という表現で十分であり、詳細な退職理由を書く必要はありません。基本的な書式は以下の通りです
- 日付
- 宛先(会社名と代表者名)
- タイトル「退職届」
- 退職の意思表示と日付
- お世話になった感謝の言葉
- 氏名(押印)
退職を伝える際は、まず直属の上司に口頭で伝え、その後退職届を提出するのが一般的です。
一身上の都合の意味は?正しい使い方・退職理由での注意点(例文あり)
退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い
失業保険はいつからもらえますか?
自己都合での退職の場合、原則として退職日の翌日から3ヶ月間の給付制限期間があります。その後、ハローワークでの失業認定を受けてから支給が始まります。
いっぽう会社都合での退職(解雇など)の場合は、7日間の待機期間後から受給可能です。
失業保険を受給するためには、退職前の2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。新卒1年目の場合、この条件を満たしていない可能性があるため注意が必要です。
会社都合退職とは何?自己都合退職との違い、メリットデメリット、失業保険や退職金も解説!
退職するときに引き止められない理由13選|伝え方のコツや事前準備などを徹底解説
まとめ

新卒で仕事を辞めたいと感じることは決して珍しくありません。業務内容とのミスマッチ、人間関係のストレス、労働条件への不満など様々な理由が考えられます。
「すぐに辞めるのは甘え」という意見もありますが、体調やメンタルの悪化、パワハラ・モラハラの被害、将来性の欠如などのケースでは退職を検討すべきでしょう。
一方で、退職を決断する前に、誰かに相談する、適性を見直す、転職先の見込みを確認するなどの冷静な判断が必要です。辞めないことで得られるスキルや自信というメリットと、辞めることで生じる転職上の不利益やリスクを天秤にかけて決断することが大切です。
退職するならこれらの記事もまるっとチェック♪
・退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い
・職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き
・在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など
・中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント
履歴書・職務経歴書の書き方も丸っとチェック♪
・履歴書の書き方完全ガイド|見本付きで履歴書作成方法を全て解説!
・履歴書の志望動機の書き方完全解説|20種以上の職種別例文付き、書き出しのコツやNG例も

監修者:島伸明
株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。
タグから見つけるTAGS
- AI面接練習 (1)
- popular (1)
- Yagishのサービス (1)
- エンジニア (16)
- キャリア (3)
- キャリアセンター (1)
- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)
- ビジネスマナー (16)
- ビジネス用語 (3)
- メール (23)
- ヤギオファー (3)
- ヤギッシュ (4)
- ヤギッシュの使い方 (1)
- 中途 (17)
- 中途向け履歴書の書き方 (3)
- 事務職 (5)
- 人気記事 (0)
- 保育士 (7)
- 公務員 (1)
- 営業 (2)
- 履歴書 (72)
- 履歴書学歴 (1)
- 志望動機 (38)
- 悩み (6)
- 新卒 (41)
- 新卒向け履歴書の書き方 (4)
- 派遣 (1)
- 看護師 (1)
- 第二新卒 (6)
- 職務経歴書 (12)
- 英語 (4)
- 転職 (7)
- 辞めたい (3)
- 退職 (18)
- 退職代行 (2)
- 退職届 (0)
- 退職届・退職願 (8)
- 送付状 (1)
- 逆質問 (1)
- 面接 (16)

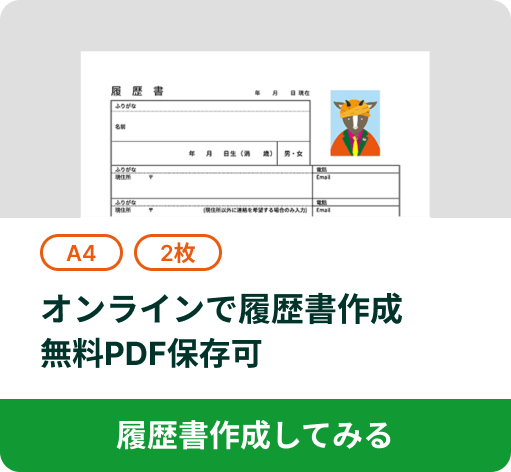
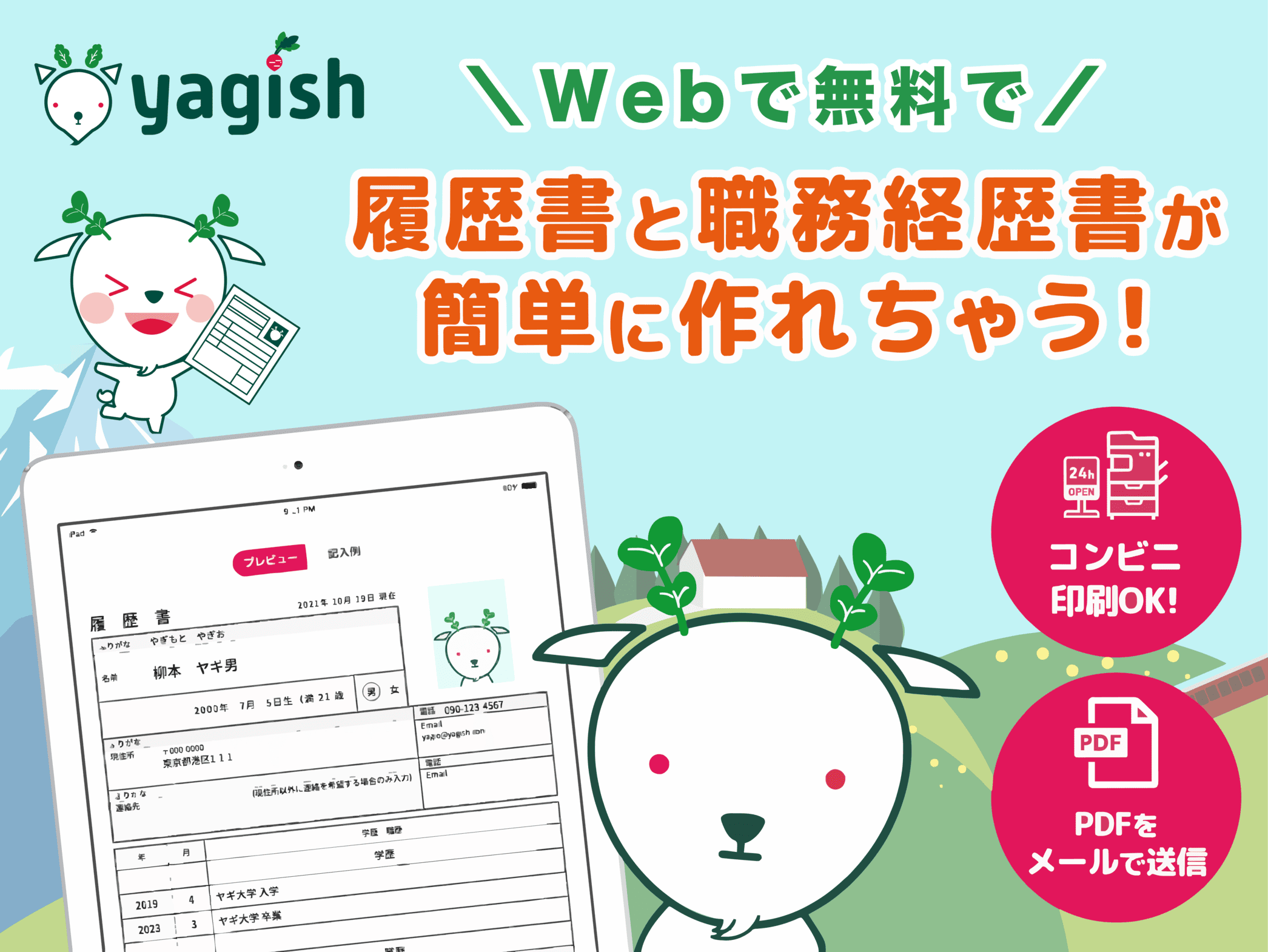
 ノウハウ一覧
ノウハウ一覧