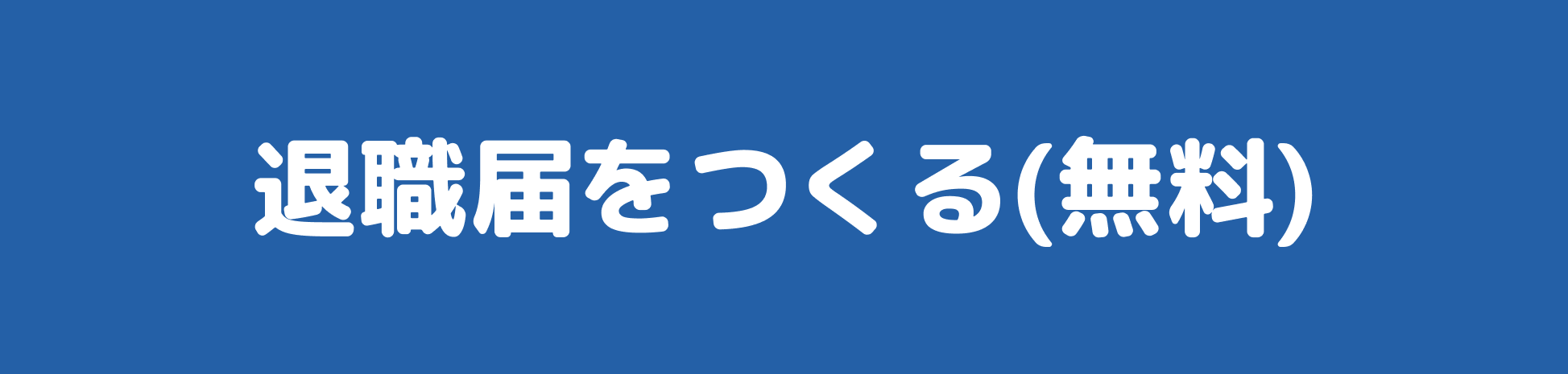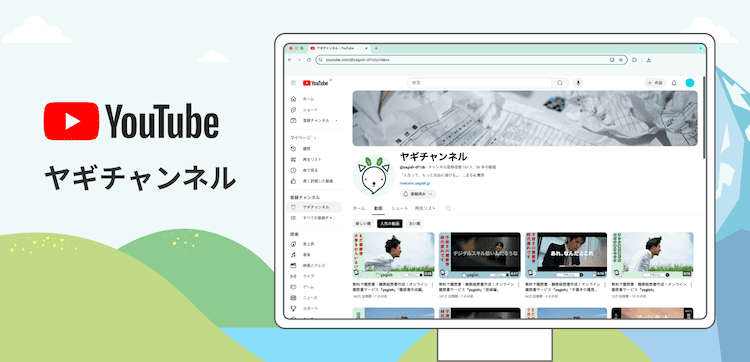2025.06.30
【ケース別】退職や転職で引き止められた時の断り方は?相手側がしつこい時の対処法
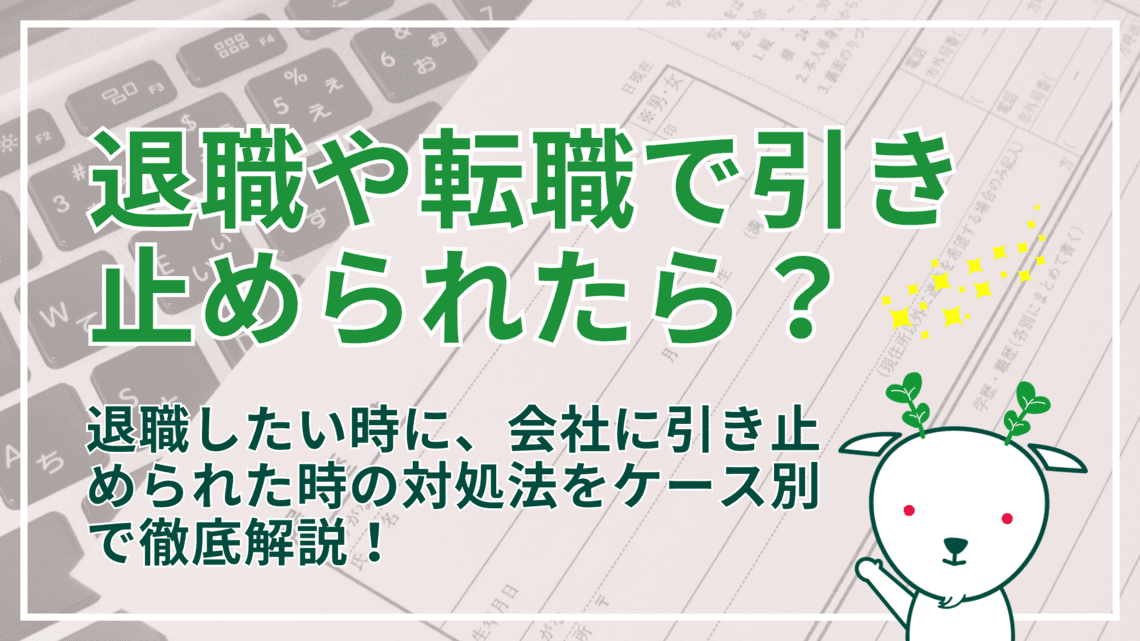
「退職の引き止めがしつこくて悩んでいる」
「辞めたいと伝えたのに、説得されて困っている」
と会社の退職の引き止めで悩んでいませんか。
- どう断れば角が立たない?
- 情に訴えられたときはどうする?
- 引き止めを拒否しても大丈夫?
など疑問が出てきます。
強い退職の引き止めに対して適切に対処しないと、退職や転職のタイミングを逃してしまうこともあります。
この記事では、退職時の引き止めへの断り方や対処法をケース別に詳しく解説します。
▼無料で作成、PDFも受け取れる!オンライン履歴書Yagish▼
【ケース別】退職や転職で引き止められたときの断り方

退職や転職の意思を伝えた際、会社から引き止めにあうことは少なくありません。
会社側もさまざまな理由で引き止めを行うため、状況に応じた適切な対応が必要です。
ここでは、よくある引き止めのケースと、それぞれの状況でスムーズに退職・転職を実現するための具体的な対応方法を解説します。
待遇改善や昇進を持ちかけられた場合
この退職の引き止め方は、優秀な人材の流出を防ぎたい、新たな採用コストをかけたくないという会社側の意図が背景にあります。
まず冷静に内容を吟味し、口頭での約束は後から反故にされるリスクがあるため、提示された条件は必ず書面で具体的な内容を確認するように求めましょう。
今回の転職理由が単に待遇面だけではなかったことを再確認し、提示された条件が本当にあなたのキャリアプランや将来の目標と合致するのかを深く考える必要があります。
もし、待遇以外の理由が退職の大きな要因であるならば、一時的な待遇改善では根本的な問題解決にはなりません。
安易に受け入れてしまうと、数ヶ月後に再び同じ不満を抱え、退職を検討することになりかねません。
「辞められると困る」と情に訴えられた場合
上司や同僚から個人的な感情や会社への貢献を理由に引き止められることがあります。
この退職の引き止め方は、責任感や義理人情に訴えかけ、退職を思いとどまらせようとするものです。
会社への感謝の気持ちを伝えつつも、退職は熟考した上での個人的な決断であり、自身のキャリアプラン実現のために不可欠であることを明確に伝えてください。
会社にとって一時的に不便が生じることは理解を示しつつも、それは会社が解決すべき問題であり、個人のキャリアを犠牲にする理由にはならないという毅然とした姿勢を見せることが重要です。
転職のリスクを強調されて不安を煽られた場合
この退職の引き止め方は、転職に伴うリスクを過度に強調し、あなたの不安を煽ることで引き止めようとするケースです。
未知への不安を利用して、現状維持を促す会社側の手段です。
この引き止めに対しては、あなたが事前に転職活動で十分な情報収集を行い、リスクを認識した上で決断していることを明確に伝えることが有効です。
自身の決断に自信を持っていることを示すことが重要で、客観的な情報に基づいた判断であることを伝えれば、相手もそれ以上強く引き止めることは難しくなります。
強引・脅し・損害請求を示唆された場合
この退職の引き止め方は、最も悪質なケースとされ、強引な引き止めや脅し、さらには損害賠償請求を示唆されることがあります。
この引き止めは、違法行為に当たる可能性が高く、労働者の退職の自由を不当に侵害するものです。
このような状況に直面した場合、決して感情的にならず、一人で抱え込まずに冷静に対処することが何よりも重要です。
このような状況では、決して一人で抱え込まず、身を守るためにも外部の専門家を頼ることをおすすめします。
>【18の例文付き】退職理由の上手な伝え方は?上司が納得・好印象を与えるコツ
退職の引き止めをスムーズに断るための伝え方

退職の引き止めにあった際、自身の退職意思を明確に、かつ冷静に伝えることです。
感情的になったり、曖躇な態度を取ったりすると、相手に「まだ説得できる」という隙を与えてしまいます。
感謝の気持ちを伝えつつも、決意の固さを伝える具体的な方法を、口頭とメール・文書に分けて解説します。
口頭での伝え方
口頭で退職の引き止めを断る際は、感情的にならず冷静に対応しましょう。
効果的な口頭での伝え方の基本構成は、
- 感謝の気持ちを述べる
- 退職理由を簡潔に説明する
- 意志の固さを示す
- 今後の協力姿勢を示す
という流れです。
例えば「○○課長には大変お世話になり、心から感謝しております。しかし、今回の退職は慎重に検討した結果の決断であり、意志は変わりません。引き継ぎについては責任を持って対応させていただきます」というような伝え方が適切です。
引き止めの理由が待遇改善や昇進の提案であった場合は、「ありがたいお話ですが、今回の決断は待遇面だけでなく、総合的に判断した結果です」と答えましょう。
具体的な会話例
「〇〇部長、お引き止めいただき、大変光栄に思います。御社には大変お世話になり、心から感謝しております。しかし、今回の退職は熟慮を重ねた上での決断であり、私の新たなキャリアプランにおいて不可欠なステップと考えております。
大変恐縮ではございますが、この決意は変わりません。残りの期間で、精一杯引き継ぎ業務に努めさせていただきますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。」
メール・文書での伝え方
口頭でのやり取りが難しい場合や、自身の意思をより明確に、かつ証拠として残したい場合には、メールや文書を活用することも有効です。
特に、退職願や退職届を提出する際は、書面での意思表示が必須となります。
メールや文書で退職の意思を伝える際は、件名で内容がわかるようにし、本文では簡潔に、かつ丁寧に退職の意思と退職希望日を明記します。
退職の意思を伝えるメール例文
件名:退職のご報告(氏名)
〇〇部長
いつも大変お世話になっております。〇〇部の〇〇です。
私事ではございますが、この度、一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご報告申し上げます。
これまで〇年間、御社で多くの貴重な経験をさせていただき、心より感謝申し上げます。特に〇〇部長には、日頃より多大なるご指導を賜り、大変お世話になりました。
退職にあたり、皆様にはご迷惑をおかけすることと存じますが、残りの期間で業務の引き継ぎを責任をもって行い、円滑な移行に努めてまいります。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、御社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
署名
感謝を伝えるフレーズ
退職の引き止めを断る際に使える具体的なフレーズを、状況別に整理すると以下のようになります。
これらのフレーズを参考に、自分の状況に合わせてアレンジして使用しましょう。
| 状況 | 効果的なフレーズ例 |
|---|---|
| 基本的な断り方 | 「ご配慮いただき心から感謝しておりますが、今回の決断は変わりません」 |
| 待遇改善の提案時 | 「ありがたいご提案ですが、今回の退職は待遇面以外の理由によるものです」 |
| 情に訴えられた時 | 「お気持ちは痛いほど理解しておりますが、自分の将来のために必要な決断です」 |
| 責任感に訴えられた時 | 「責任は十分感じておりますが、引き継ぎを完璧に行うことで責任を果たします」 |
| 転職先について聞かれた時 | 「新しい環境で挑戦したいという気持ちが強く、意志は固まっております」 |
これらのフレーズを組み合わせることで、相手への敬意を示しながらも、自分の意志をしっかりと伝えることができます。
重要なのは、相手の立場や感情に配慮しつつ、曖昧さを残さない明確なコミュニケーションを心がけることです。
>退職日は月末にしないほうが得?損?理由と月途中の退職メリットを解説
退職を引き止められたときにやってはいけない対応

退職や転職を引き止められたときは、つい感情的になってしまいます。
引き止めに合っていると、どうしても心が揺らぎ、曖昧な返答をしがちです。
上手に辞めるためにも、以下で解説するやってはいけないNGな対応を参考にしてください。
曖昧な返答
退職の引き止めをされた際、曖昧な返答は誤った期待を抱かせ、結果として引き止めが長引く原因となります。
| NGな返答例 | 起こりうる結果 |
|---|---|
| 「検討します」「考えておきます」 | 会社に「引き止める余地がある」と誤解を与え、引き止めが長期化します。 |
| 「〇〇が改善されれば残るかもしれません」 | 会社が改善策を具体的に提示し、退職の意思が固まっていないと判断され、交渉が複雑化します。 |
| 「もう少し時間をください」 | 会社に引き止め策を練る時間を与え、より強力な引き止めに発展する可能性があります。 |
また、「〇〇が改善されれば残るかもしれません」といった条件付きの返答も、会社がその条件をクリアしようと具体的な改善策を提示してくるため、退職の意思が固いにもかかわらず、交渉の泥沼にはまることになりかねません。
退職の意思が固いのであれば、たとえ引き止めにあっても、その場で明確に断ることが重要です。
曖昧な態度は、最終的に自分自身も会社側も疲弊させ、円満な退職を妨げる要因となります。
不満を中心にしたネガティブな発言
退職理由を伝える際、現在の会社への不満や批判を中心にしたネガティブな発言は避けるべきです。
不満を理由にした場合の問題点は、会社側が「問題を解決すれば残ってくれる」と判断し、引き止めが長期化します。
さらに、ネガティブな発言は職場の雰囲気を悪化させ、退職までの期間を過ごしにくくする可能性があります。
| 避けるべき発言例 | 推奨される発言例 |
|---|---|
| 「給与が安すぎて生活が苦しい」 | 「新しい分野にチャレンジしたい」 |
| 「上司との関係が最悪」 | 「キャリアアップを目指したい」 |
| 「この会社に将来性を感じない」 | 「自分の成長のために環境を変えたい」 |
| 「仕事がつまらない」 | 「専門性を高めたい」 |
代わりに、前向きな理由や個人的な成長を軸とした説明をすることが重要です。
「新しい業界で経験を積みたい」「専門スキルを向上させたい」「ライフスタイルを変えたい」といった、会社では解決できない個人的な目標を理由とすることで、引き止めを受けにくくなります。
感情的な発言や行動
退職の引き止めにあう中で、感情的になることは避けましょう。
感情的な言動は、会社側に不信感や敵対心を与え、退職手続きがスムーズに進まなくなる原因となります。
また、感情的に会社や上司を非難することは、円満退職を妨げ、退職後の人間関係や業界内での評判にも悪影響を及ぼします。
どんなに引き止めがしつこくても、感情的にならず、一貫して冷静な態度を保つように心がけましょう。
>新卒で「辞めたい」は甘え?退職すべきかどうかの判断ポイントや注意点を解説
退職や転職の引き止めにあう4つの理由

退職の意思を伝えた際、会社から引き止めにあうことは決して珍しくありません。
これは単にあなたの退職を阻止したいというだけでなく、会社側の様々な事情が背景にあります。
引き止めにあう主な理由を理解することで、その後の対応や心構えに役立つでしょう。
優秀な人材として評価されているから
会社にとって不可欠な存在であると認識されている場合、引き止めにあう可能性は高くなります。
特定のスキルや専門知識、長年の経験、優れた実績、あるいはチームをまとめるリーダーシップなど、会社にとって手放したくない「優秀な人材」と評価されているからです。
あなたの退職は、単なる人員の減少だけでなく、会社が培ってきたノウハウや企業文化、業務遂行能力そのものの損失につながると考えられます。
人手不足・業務負担増を避けたいから
あなたの退職が、残された社員の業務負担を増やし、組織全体の生産性を低下させるリスクがある場合も、会社は強く引き止めようとします。
特に、特定の業務をあなたしか担当していない場合や、現在進行中のプロジェクトに深く関わっている場合、退職することで業務の停滞や遅延に直結しかねません。
会社は新たな人員を補充し、その人材が業務に慣れるまでの間、既存の社員に過度な負担がかかることを避けたいと考えています。
上司の評価が下がるのを避けたいから
部下の退職は、直属の上司のマネジメント能力や人事評価に直接影響を与えることがあります。
多くの企業では、部下の離職率やチームの安定性が上司の評価項目の一つとなっているため、部下の退職は上司自身の評価を下げる要因となり得ます。
そのため、上司は自身の評価を守るために、部下を引き止めようとすることがあります。
また、部下の退職によってチームの目標達成が困難になることを避けたいという意図も含まれます。
採用・教育コストをかけたくないから
新しい人材の採用と教育には、企業にとって大きなコストが発生します。
具体的には、求人広告費、採用エージェントへの手数料、採用担当者の人件費、そして新入社員が一人前になるまでの教育費用やOJT期間中の生産性低下など、目に見えるコストだけでなく、見えないコストも膨大に発生します。
会社にとって、既存の優秀な社員を引き止める方が、これらの新規採用・教育にかかるコストをかけるよりもはるかに経済的であると判断するため、引き止めに力を入れるのです。
>退職するときに引き止められない理由13選|伝え方のコツや事前準備などを徹底解説
退職を引き止められやすい人の3つの特徴

退職の意思を伝えた際に、会社から強く引き止められる人にはいくつかの共通する特徴があります。
| 特徴 | 会社が引き止める主な理由 |
|---|---|
| 優柔不断・未熟な退職理由の人 | 説得の余地があると判断されるため 退職の本気度が低いと見なされるため |
| 周囲との人間関係の良い人 | チームワークや社内連携に不可欠な存在であるため 人間関係のハブであり、士気への影響が大きいため |
| 業務での貢献度が高い人 | 代替人材の確保・育成に時間とコストがかかるため 業績やプロジェクトへの直接的な影響が大きいため |
ここでは、特に引き止められやすい人の特徴と、会社側が引き止めに動く背景をまとめました。
①優柔不断・未熟な退職理由の人
退職の意思を伝える際、理由が曖昧であったり、漠然とした不満や感情的な理由に終始する人は引き止められやすいとされます。
会社側から「まだ説得の余地がある」「一時的な感情ではないか」と判断されやすく、引き止めの対象になりやすい傾向です。
例えば、「なんとなく今の仕事に不満がある」「もっと自分に合った仕事がある気がする」といった曖昧な理由では、会社側は待遇改善や配置転換、あるいは業務内容の見直しなどを提案することで、退職を阻止できると期待します。
具体的な次のステップや明確なキャリアプランが示せない場合、会社側はあなたの退職を「問題解決で回避できるもの」と捉え、積極的に引き止めにかかるでしょう。
②周囲との人間関係の良い人
社内の人間関係が良好で、同僚や上司からの信頼が厚く、周囲から慕われている人は、退職を引き止められやすい特徴の一つです。
チーム内の潤滑油的な存在であったり、部署間の連携を円滑にする役割を担っている場合、その人の退職はチーム全体の士気や業務効率に影響を与えると懸念されます。
特に、面倒見が良い、相談役になっている、社内イベントの企画に積極的であるなど、人望がある人は、会社側が「失いたくない人材」と判断し、個人的な感情に訴えかける形で引き止めを行うケースが多く見られます。
周囲の社員からも「辞めないでほしい」と引き止められることもあり、情に流されやすい状況に陥る可能性があります。
③業務での貢献度が高い人
会社の中で貢献度の高い人は、高確率で退職を引き止められルでしょう。
例えば以下のような人物です。
- 特定の専門スキルを有している
- 重要なプロジェクトの中心人物である
- 売上に直接的に大きく貢献している
このような人材が退職すると、会社の業績や業務遂行に大きな支障をきたす可能性があるため、強く引き止められます。
特に、その人にしかできない独自のノウハウやスキルがある場合、あるいは後任の育成に多大な時間とコストがかかるポジションにいる場合、会社側は新たな人材を採用・教育するコストやリスクを避けたいと考えます。
そのため、待遇の引き上げや役職の提示、あるいは希望する業務への配置転換など、あらゆる手段を用いて退職を阻止しようとします。
>退職時の引継ぎをスムーズに行う基本やポイントを徹底解説!トラブルにならないコツ
退職の引き止めを避けて転職するための3STEP

退職や転職の意思を伝えた際に、会社から引き止めに遭うことは少なくありません。
スムーズな退職を実現し、新たなキャリアへ移行するためには、事前の周到な準備が不可欠です。
ここでは、引き止めを未然に防ぐ、あるいは最小限に抑えるための具体的な準備について解説します。
STEP1:理由を明確に整理する
退職の引き止めにあう前に、なぜ退職したいのか、なぜ転職を選んだのかという理由を自分の中で明確に整理しましょう。
単なる現状への不満だけでなく、将来のキャリアプランや自己成長といった前向きな視点から整理すると、会社側も納得しやすくなります。
特に、引き止めに遭った際に、会社からの待遇改善提案や情に訴えかける言葉に対して、ぶれることなく自身の意志を伝えるための「軸」となります。
曖昧な理由では、会社側から改善提案を引き出され、引き止めに応じざるを得ない状況に陥る可能性が高まります。
STEP2:退職時期から転職までのプランニングをする
退職の意思表示から実際に退職し、転職先での勤務を開始するまでの具体的なスケジュールを立てることも、引き止めを回避するために非常に有効です。
計画が明確であればあるほど、会社側も引き止める余地が少なくなり、スムーズな手続きへと移行しやすくなります。
以下の要素を含めて、具体的なプランニングを進めましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 退職意思表示のタイミング | 就業規則で定められた期間を確認し、余裕をもって伝える時期を決定 |
| 引き継ぎ計画 | 担当業務の洗い出し、マニュアル作成、後任者への教育など、円滑な引き継ぎのための具体的なスケジュールを立てます。 |
| 有給休暇の消化計画 | 残っている有給休暇を消化する期間を考慮に入れ、最終出社日と退職日を明確にします。 |
| 転職活動の進行状況 | 内定獲得の目処や入社希望日など、転職活動の具体的な進行状況を踏まえて、退職日を決定します。内定が出てから退職交渉に入るのが理想的です。 |
| 必要書類の確認と準備 | 離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証など、退職後に必要となる書類の受け取り時期や方法を確認します。 |
これらの計画を具体的な日付とともに立てておくことで、会社側に対して「既に具体的な次のステップに進む準備ができている」という強い意志を示すことができます。
STEP3:就業規則の確認と手続きをする
退職に関する会社の就業規則を事前に確認することは、法的なトラブルを避け、スムーズな退職を実現するために不可欠です。
特に、退職の意思表示期間、退職金に関する規定、有給休暇の取得条件などは必ず確認しておきましょう。
就業規則に則って手続きを進めることで、会社側が「規則違反」を理由に引き止めたり、退職を拒否したりする余地をなくすことができます。
また、退職時に会社に返却すべきものや、会社から受け取るべき書類についても確認し、手続きを進める準備を進めておきましょう。
適切な手続きを踏むことで、会社側も納得せざるを得ない状況を作り出すことが可能です。
>仕事辞めてから転職?働きながら転職活動?それぞれのメリット
退職の引き止めを法的に対処する方法

退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社からの引き止めが強引であったり、不当な要求や脅しめいた言動があったりする場合には、法的な手段を検討する必要があります。
ご自身の権利を守り、円滑な退職を実現するために、以下の方法を参考にしてください。
就業規則・労働契約書に基づく主張をする
まずはご自身の会社の就業規則や労働契約書を確認し、それに従って退職の意思表示をしていることを明確に主張しましょう。
労働者には、民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも退職の申し入れができる自由が保障されています。
これは「退職の自由」と呼ばれ、会社が一方的に退職を拒否することはできません。
多くの企業では、就業規則や労働契約書に「退職の際は〇ヶ月前までに申し出ること」といった退職に関する規定が設けられています。
弁護士を活用する
会社からの引き止めがエスカレートし、損害賠償請求を示唆されたり、退職を認めないといった強硬な態度が続いたりする場合には、弁護士への相談を検討すべきです。
弁護士は法律の専門家として、以下のようなサポートを提供してくれます。
- 法的な根拠に基づいた適切なアドバイス
- 会社への内容証明郵便の送付による退職意思の明確化
- 会社との交渉代行
- 万が一、訴訟に発展した場合の代理人
弁護士に依頼することで、会社側も法的な対応を迫られることになり、不当な引き止めが収束する可能性が高まります。
精神的な負担も軽減されるため、状況が深刻な場合は早期の相談を検討してください。
退職代行サービスを活用する
退職代行サービスは、労働者に代わって会社に退職の意思表示を行うサービスです。
直接会社と話すことなく退職手続きを進められるため、パワハラを受けている場合や精神的な負担を軽減したい場合に効果的です。
退職代行サービスを選ぶ際は、運営主体に注意が必要です。
弁護士が運営する退職代行サービスであれば、法的な交渉も可能ですが、一般企業が運営するサービスでは退職の意思表示の代行のみに限られます。
| 運営主体 | 費用相場 | 対応可能範囲 |
|---|---|---|
| 一般企業 | 2万円〜5万円 | 退職の意思表示のみ |
| 労働組合 | 2万円〜3万円 | 会社との交渉も可能 |
| 弁護士 | 5万円〜10万円 | 法的手続き全般 |
退職代行サービスを利用する場合でも、事前に必要な書類や私物の整理は済ませておく必要があります。
労働基準監督署への相談をする
会社からの引き止めが、労働基準法に違反するような行為(例:未払い賃金の発生、ハラスメント、不当な労働条件の強制など)を伴う場合は、労働基準監督署に相談することができます。
労働基準監督署は、労働基準法に基づき、企業が法律を遵守しているか監督する機関です。
労働基準監督署は、労働者からの申告を受けて、会社に対して指導や是正勧告を行うことがあります。
ただし、労働基準監督署は個別の民事紛争には直接介入しないため、退職の意思を会社に伝えることや、会社との交渉を代行することはできません。
あくまで労働基準法違反が疑われる場合に有効な相談先であることを理解しておきましょう。
証拠の収集と記録をする
会社との間で法的なトラブルに発展した場合に備え、引き止めに関する証拠を収集し、記録しておくことと効果的です。
客観的な証拠があることで、ご自身の主張の信頼性が高まり、有利に交渉を進めることができます。
以下のようなものを証拠として残しておきましょう。
- 退職の意思を伝えた日時、相手、内容
- 引き止めの具体的な内容
- 引き止めによって受けた精神的・身体的苦痛に関する記録
- 就業規則や労働契約書
- 給与明細やタイムカードなど、労働条件に関する資料
証拠は、日時、場所、相手、具体的な内容を明確に記録することがポイントです。これにより、後から事実関係を正確に証明できるようになります。
>退職時の引継ぎをスムーズに行う基本やポイントを徹底解説!トラブルにならないコツ
退職や転職の引き止めに関連するよくある質問

退職の引き止めは違法ですか?
退職の引き止め行為自体が違法となるわけではありません。
企業が従業員の退職を思いとどまらせるために、待遇改善を提案したり、業務の継続を懇願したりすることは、一般的に許容される範囲内の行為とされています。
しかし、その引き止め行為が以下のような場合は、違法となる可能性があります。
| 違法な引き止め行為 | 法的根拠 |
|---|---|
| 退職を認めない | 労働基準法第5条(強制労働の禁止) |
| 損害賠償を請求する | 労働基準法第16条(賠償予定の禁止) |
| 脅迫や恫喝を行う | 刑法第222条(脅迫罪) |
| 退職金の不当な減額 | 労働基準法第89条(就業規則) |
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は原則として2週間前に申し出れば退職できると定められています。
会社が不当に退職を妨げることは、労働者の権利を侵害する行為にあたります。
退職するときに言ってはいけないことは?
退職を伝える際には、円満退職を目指すためにも、避けるべき発言がいくつかあります。
以下に、特に注意すべき点は以下の内容です。
- 会社や上司・同僚の不満や愚痴
- 給与や待遇の不満
- 曖昧な返答や優柔不断な態度
- 転職先の情報
- 引継ぎを拒否するような発言
これらの発言を避けることで、最後まで責任感ある姿勢を保ち、円滑な退職を実現しやすくなります。
退職の引き止めはいつまでされてもいいの?
法的には、労働者が退職の意思を明確に伝えた後、会社がいつまでも引き止めを続けることに明確な期限の定めはありません。
民法第627条第1項により、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は2週間前までに退職の申し入れをすれば、その2週間が経過した時点で雇用契約は終了します。
会社の就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出ること」といった規定があったとしても、この民法の規定が優先される場合が多いです。
会社が2週間を超えて不当に退職を妨害し続ける場合や、引き止め行為がハラスメントに該当するような場合は、労働基準監督署や弁護士への相談、あるいは退職代行サービスの利用を検討すべき状況と言えます。
退職を1ヶ月前に伝えても辞めさせてくれない場合は?
期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の意思表示をしてから2週間が経過すれば退職できると定められています。
したがって、就業規則で「退職は1ヶ月前に申し出ること」と定められていたとしても、会社が退職を認めない場合は、民法の規定を根拠に退職を主張することが可能です。
会社が退職を拒否し続ける場合、以下の対応を検討してください。
- 内容証明郵便で退職届を送付する
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談する
- 退職代行サービスを利用する
いずれの対応を取るにしても、退職の意思を明確に伝え、書面などで記録を残しましょう。
退職する最悪のタイミングはいつですか?
退職のタイミングは、円満退職や自身のキャリアプランに大きく影響します。
以下のようなタイミングでの退職は、会社や周囲に大きな負担をかけたり、自身に不利益が生じたりする可能性があるため、避けるべきとされています。
- 会社の繁忙期や重要なプロジェクトの進行中
- 賞与(ボーナス)支給直前
- 人事異動や組織変更の直後
- 後任者が全く決まっていない、または引き継ぎが全くできない状況
- 試用期間中
これらのタイミングを避けることで、会社への影響を最小限に抑え、円滑な退職を実現しやすくなります。
>退職届に印鑑は必要?シャチハタなど印鑑の種類や失敗した時の対処法を解説
まとめ
退職時の引き止めは、優秀な人材の流出防止や人手不足回避などの理由で発生しますが、適切な対応により円滑に断ることができます。
待遇改善の提案には冷静に判断し、情に訴えられても毅然とした態度を保ち、脅しには法的対処を検討しましょう。
明確な退職理由の整理と事前準備、就業規則の確認が重要です。
しつこい引き止めには弁護士相談や退職代行サービスの活用も有効な選択肢となります。
退職するならこれらの記事もまるっとチェック♪
・退職届・退職願の書き方完全ガイド|テンプレート、手書き例文、辞表との違い
・職務経歴書と履歴書での「退職理由・転職理由」の書き方徹底解説!例文付き
・在職中の転職活動での履歴書の書き方ガイド|現在に至る、退職予定日、以上など
・中途採用1年で退職はアリ?転職市場の現状と不安解消のポイント
ビジネスマナーも学ぶ♪
・【例文付き】新卒が履歴書をメールで送る際のマナーと書き方、注意点
・「弊社」「当社」「自社」の違いとは?徹底解説!使い分け方、メールでの例文や注意点
・「御社」「貴社」の違い・使い分けを徹底解説!メール・履歴書・面接での使い方ガイド
面接の関連記事もチェック♪
・中途採用面接でよくある質問40選と回答例文|服装やマナー、面接の流れも。
・面接官の心をつかむ!面白い逆質問の例文リスト、NG質問や注意点など
・転職面接のおすすめ逆質問50選|好印象を与える質問例&NG質問を紹介!
・【面接|新卒の逆質問例35選】一次や最終面接で有利に進むポイントと注意点
履歴書作成の関連記事をチェック♪
>履歴書の書き方完全ガイド|見本付きで履歴書作成方法を全て解説!
>【例文付き】履歴書の志望動機の書き方・基本を完全解説!未経験や新卒、転職向けのコツ
>履歴書をPDF化する方法|簡単3ステップ!作成からダウンロードまで
>履歴書の職歴が多くて書ききれない時の7つの対処法と書き方完全ガイド
>[全10種]履歴書無料テンプレートPDFダウンロード!スマホ・PCで作成可能
職務経歴書もチェックしてみよう♪

監修者:島伸明
株式会社Yagishの取締役CMO。履歴書作成サービス「Yagish(ヤギッシュ)」の成長を牽引し、2024年には800万UUを突破、会員登録者数160万人を達成するなど、日本のキャリア支援市場で高い実績を誇る。大手企業での新規事業・海外事業に加え、複数の企業で取締役を歴任。事業企画、EC、エンタメ、ゲーム開発、マーケティング、コンサルティングと多岐にわたる分野で豊富な経験を持ち、キャリア形成に深い知見を持つ。
タグから見つけるTAGS
- AI面接練習 (1)
- popular (1)
- Yagishのサービス (1)
- エンジニア (16)
- キャリア (3)
- キャリアセンター (1)
- バイトパート向け履歴書の書き方 (2)
- ビジネスマナー (16)
- ビジネス用語 (3)
- メール (23)
- ヤギオファー (3)
- ヤギッシュ (4)
- ヤギッシュの使い方 (1)
- 中途 (17)
- 中途向け履歴書の書き方 (3)
- 事務職 (5)
- 人気記事 (0)
- 保育士 (7)
- 公務員 (1)
- 営業 (2)
- 履歴書 (72)
- 履歴書学歴 (1)
- 志望動機 (38)
- 悩み (6)
- 新卒 (41)
- 新卒向け履歴書の書き方 (4)
- 派遣 (1)
- 看護師 (1)
- 第二新卒 (6)
- 職務経歴書 (12)
- 英語 (4)
- 転職 (7)
- 辞めたい (3)
- 退職 (18)
- 退職代行 (2)
- 退職届 (0)
- 退職届・退職願 (8)
- 送付状 (1)
- 逆質問 (1)
- 面接 (16)

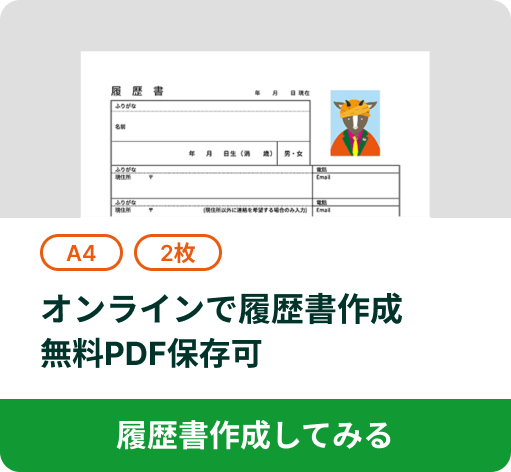
 ノウハウ一覧
ノウハウ一覧