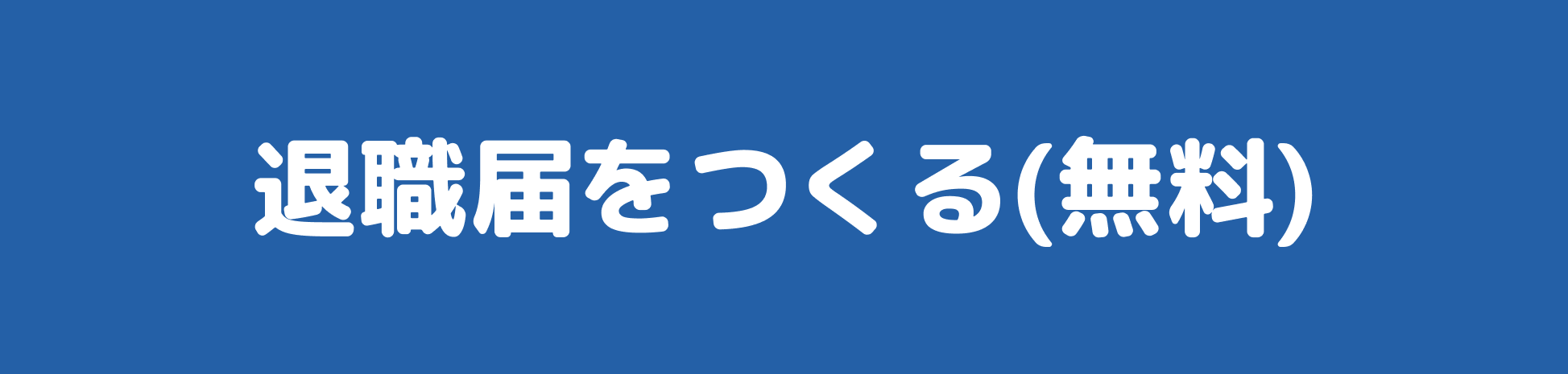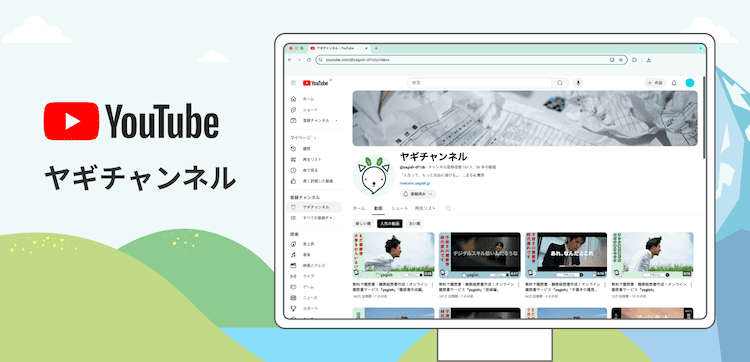まず、有給休暇とは?4つのポイント

退職時に有給休暇(有休)を消化したいと考えている方は多いでしょう。しかし、有給休暇の仕組みをきちんと理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは、有給休暇の基本的な4つのポイントについて解説します。
長期勤務者は有給をより多く持っている
有給休暇は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。
労働基準法では、6ヶ月継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。
その後、勤続年数が増えるごとに付与日数も増加し、6年6ヶ月以上勤務した場合には年間20日の有給休暇が付与されます。つまり、長く勤めれば勤めるほど、退職時に消化できる有給休暇の日数も多くなるのです。
具体的な勤続年数と法定の有給休暇日数の関係は以下の通りです。
- 6ヶ月:10日
- 1年6ヶ月:11日
- 2年6ヶ月:12日
- 3年6ヶ月:14日
- 4年6ヶ月:16日
- 5年6ヶ月:18日
- 6年6ヶ月以上:20日
ただし、これはあくまで法定の最低日数であり、会社によってはより多くの有給休暇を付与している場合もあります。自分がどれだけの有給休暇を持っているかは、退職前に必ず確認しておきましょう。
有給は何日取れるもの?
有給休暇は、上記で説明した勤続年数に応じた日数が付与されますが、実際に何日取得できるかは、残日数と会社の規定によって異なります。法律上は、付与された有給休暇は全て取得することが可能です。
有給休暇は自由に取れる?
労働基準法では、労働者が請求する時季に有給休暇を与えることを原則としています。つまり、基本的には労働者の希望する日に有給休暇を取得することができます。
しかし、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社は時季変更権を行使して、別の日に有給休暇を取るよう変更を求めることができます。例えば、繁忙期や重要なプロジェクトの締め切り直前、人手が足りない時期などがこれに該当します。
有給に期限・時効はある?
有給休暇には時効があります。労働基準法では、有給休暇の時効は「付与日から2年間」と定められています。つまり、付与された有給休暇は2年間使わなければ失効してしまいます。
例えば、2022年4月に付与された10日間の有給休暇は、2024年3月末までに使用しなければ失効します。そのため、長期間有給休暇を取得せずに貯めてきた場合、古いものから順に失効していくことになります。
退職時にまとめて有休完全消化する6つの方法

退職が決まったら、残っている有給休暇を消化したいと考える方は多いでしょう。しかし、ただ「有給を使いたい」と言うだけでは、スムーズに消化できないこともあります。
会社の就業規則をまず読む
有給休暇の消化方法を考える前に、まずは自社の就業規則を確認しましょう。就業規則には、有給休暇の取得方法や退職時の取り扱いについて記載されていることがあります。
就業規則は通常、会社の共有フォルダやイントラネット、人事部門で閲覧できることが多いです。
自分の有給休暇はいくらあるかを確認
次に、自分がどれだけの有給休暇を持っているのかを正確に把握しましょう。勤続年数によって付与される有給日数は異なりますし、前年度からの繰越分がある場合もあります。
退職までのスケジュールを作る
有給休暇を消化するためには、退職までの具体的なスケジュールを立てることが重要です。退職予定日から逆算して、業務の引き継ぎ期間や有給消化期間を設定しましょう。
通常、退職の申し出は1ヶ月前が一般的ですが、管理職やキーパーソンの場合は2〜3ヶ月前に伝えることが望ましいとされています。その後、引き継ぎ期間を経て有給消化期間に入るというのが一般的な流れです。
ですが多くの有給がある場合はもっと早くに動き始める必要があります。
>退職を伝える最適なタイミングは?上司や同僚に伝える、円満退職のポイント
最終出社日までに有給消化する場合
最終出社日までに有給休暇を消化する場合は、退職日の前に有給休暇を取得して出社しないという方法です。例えば、3月末で退職予定で20日の有給がある場合、3月1日〜3月30日までを有給休暇とし、最終出社日を2月末とする方法です。
この方法のメリットは、退職手続きをすべて最終出社日に済ませることができ、退職後に会社に戻る必要がないことです。社員証や会社の備品の返却、退職金や最終給与の手続きなどをすべて最終出社日に完了させることができます。
ただし、この方法を選ぶ場合は、最終出社日までに業務の引き継ぎを完全に終わらせる必要があります。また、有給休暇中に緊急の連絡が入る可能性があるため、連絡手段を確保しておくとよいでしょう。
最終出社日が終わってから有給消化する場合
もう一つの方法は、通常通り出社し、業務引き継ぎなどをすべて終えてから有給休暇を取得する方法です。この場合、例えば3月末退職予定であれば、3月15日までは通常勤務し、3月16日〜3月31日を有給休暇とするようなスケジュールになります。
この方法のメリットは、業務の引き継ぎや残務処理を確実に行えることです。また、同僚や上司との最後の挨拶も丁寧に行えるため、円満な退職につながりやすいでしょう。
ただし、この方法では退職手続きを有給休暇取得前に済ませておく必要があります。また、有給消化中に突発的な問い合わせが発生する可能性も考慮し、連絡方法を決めておくことをおすすめします。
>退職時の挨拶メールの書き方|宛先別や社内外の例文、マナーを徹底解説!
有給完全消化のためには早めに準備する

有給休暇を完全に消化するためには、早めの準備が不可欠です。一般的には、退職を考え始めた時点で有給消化の計画も立て始めるとよいでしょう。
上司としっかり確認する
有給休暇の消化計画ができたら、まずは直属の上司に相談しましょう。退職の意向と共に、有給休暇の消化希望も伝えることが重要です。
例えば、「3月末で退職を考えており、3月の前半まで通常勤務して引き継ぎを行い、残りの期間を有給休暇として取得したいと考えています」といった具体的な提案をするとよいでしょう。
業務引き継ぎをしっかり終わらせる
有給休暇を円滑に消化するためには、業務の引き継ぎをしっかり行うことが不可欠です。引き継ぎが不十分だと、有給休暇中に問い合わせが殺到したり、最悪の場合、有給消化を断られたりすることもあります。
効果的な引き継ぎを行うためには、まず担当業務の棚卸しを行いましょう。日常的な業務、定期的な業務、イレギュラーな対応が必要な業務など、すべてを書き出します。
退職時の有休消化で起こりうるトラブルと解決方法

退職時に有給休暇を消化しようとすると、様々なトラブルに直面することがあります。退職を円滑に進めるためには、これらのトラブルをあらかじめ想定し、適切な対処法を知っておくことが大切です。
上司に「有給休暇の消化はだめ」と言われた
退職の意思を伝えた際、上司から「有給休暇の消化はできない」と言われるケースがあります。しかし、労働基準法では従業員の有給休暇取得は法的に保障されており、会社側が消化を拒否することは原則としてできません。
この場合の対処法としては、「労働基準法では有給休暇の取得は労働者の権利として認められています」と伝えましょう。それでも拒否される場合は、人事部門に相談するか、最終的には労働基準監督署に相談することも検討できます。
ただし、業務の引き継ぎ状況や会社の繁忙期などによっては、有給休暇の取得時期について会社側と話し合いを行うことも大切です。お互いが納得できる形で解決を目指しましょう。
最終出勤日の引き伸ばしを打診された
「もう少し長く働いてほしい」「引き継ぎが終わるまで退職日を延期してほしい」と言われるケースもあります。これは会社側の業務上の都合によるものですが、あなたの退職計画に影響を与える可能性があります。
こうした要請があった場合、まずは自分の予定や次の就職先との約束を考慮しましょう。無理なく対応できる範囲であれば、協力することで円満退社につながることもあります。しかしあなたの権利としては、会社のために有給消化量を減らす必要はありません。
重要なのは、感情的にならず、冷静に交渉することです。会社との関係性を良好に保ちつつ、自分の権利も守るバランス感覚が大切です。
退職までの引き継ぎがうまくいかず終わらない
有給休暇の消化を希望していても、引き継ぎ業務が終わらないため、「引き継ぎが終わるまで有給は使えない」と言われることがあります。これは特に専門性の高い仕事や、長期間担当していた業務の場合に起こりやすい問題です。
この問題を防ぐためには、計画的な引き継ぎスケジュールを立てることが重要です。退職の意思を伝えた時点で、詳細な引き継ぎ計画を作成し、上司や後任者と共有しましょう。業務マニュアルの作成やチェックリストの準備も効果的です。
退職までに有給休暇が半分しか消化できそうにない
業務の都合や引き継ぎの状況により、持っている有給休暇すべてを消化できないケースもあります。例えば、20日の有給があるのに、10日分しか消化できないといった状況です。
また、有給休暇の一部を消化し、残りを買い取ってもらうという折衷案も検討価値があります。例えば、20日のうち10日は実際に休暇として取得し、残り10日分は金銭で補償してもらうといった方法です。
有給のはずが普通の休暇とされた
退職前に取得した休暇が、後から「欠勤」や「無給の休暇」として扱われるというトラブルもあります。これは給与計算時に気づくことが多く、最終的な給与が予想より少なくなるという形で表れます。
このトラブルを防ぐためには、有給休暇を申請する際に必ず書面やメールなど、記録に残る形で行うことが重要です。「○月○日から○月○日まで、退職前の有給休暇として取得します」と明記し、上司や人事部門の承認をもらっておきましょう。
もし実際にこのトラブルが発生した場合は、申請時の記録を示しながら人事部門に確認を求めてください。書面での記録があれば、誤解の解消は比較的容易です。
退職前の有給休暇でのQ&A

退職を考えている方にとって、有給休暇の消化は大きな関心事です。ここでは、退職前の有給休暇に関する一般的な疑問にお答えします。
有給休暇の買取ってありうる?
法律上、有給休暇の買取は原則として認められています。
ただし、買取については以下の点に注意が必要です。
まず退職時を除いて在職中の有給休暇買取は違法とされています。これは使用者が金銭的補償を提示することで、労働者の休暇取得を抑制する可能性があるためです。
ただ会社によっては就業規則で「有給休暇の買取は行わない」と定めているケースもあるため、自社の規定を確認することをお勧めします。
有休消化中にボーナスをもらうことは可能?
有給休暇消化中のボーナス受給については、会社の規定によって異なります。基本的に以下のケースが考えられます。
一般的に、有給休暇は労働したものとみなされるため、有休消化中であってもボーナスの算定対象期間に含まれます。
ただし、ボーナスの支給条件として「支給日に在籍していること」という規定がある会社も多く存在します。この場合、有給休暇消化中に支給日を迎えても、すでに退職扱いになっていればボーナスを受け取れない可能性があります。
>支給日前に退職、退職予定だとボーナスはもらえない?ベストな退職時期とは?
有休消化中に次の転職先で働き始めてもいい?
有給休暇消化中に次の転職先で働き始めることができるかどうかは、法的には可能ですが、いくつかの注意点があります。
まず、法律上の観点からは、有給休暇中であっても原則として他社で就労することは禁止されていません。有給休暇は労働者の自由に使える権利だからです。

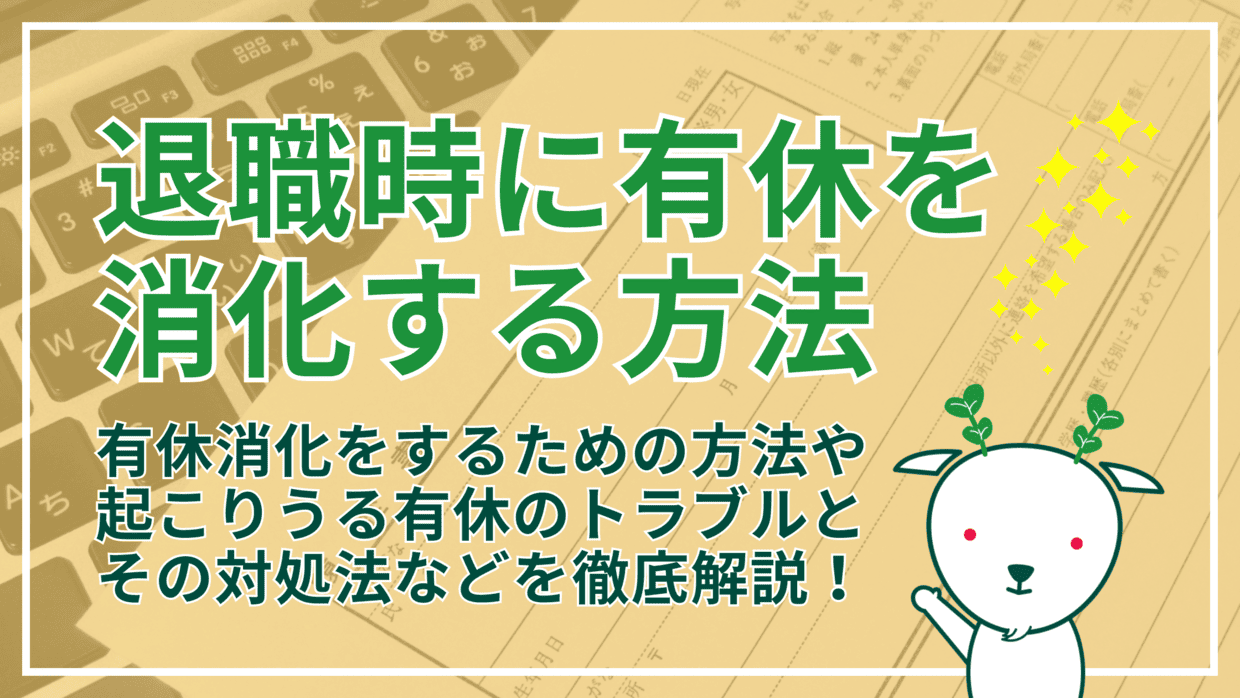
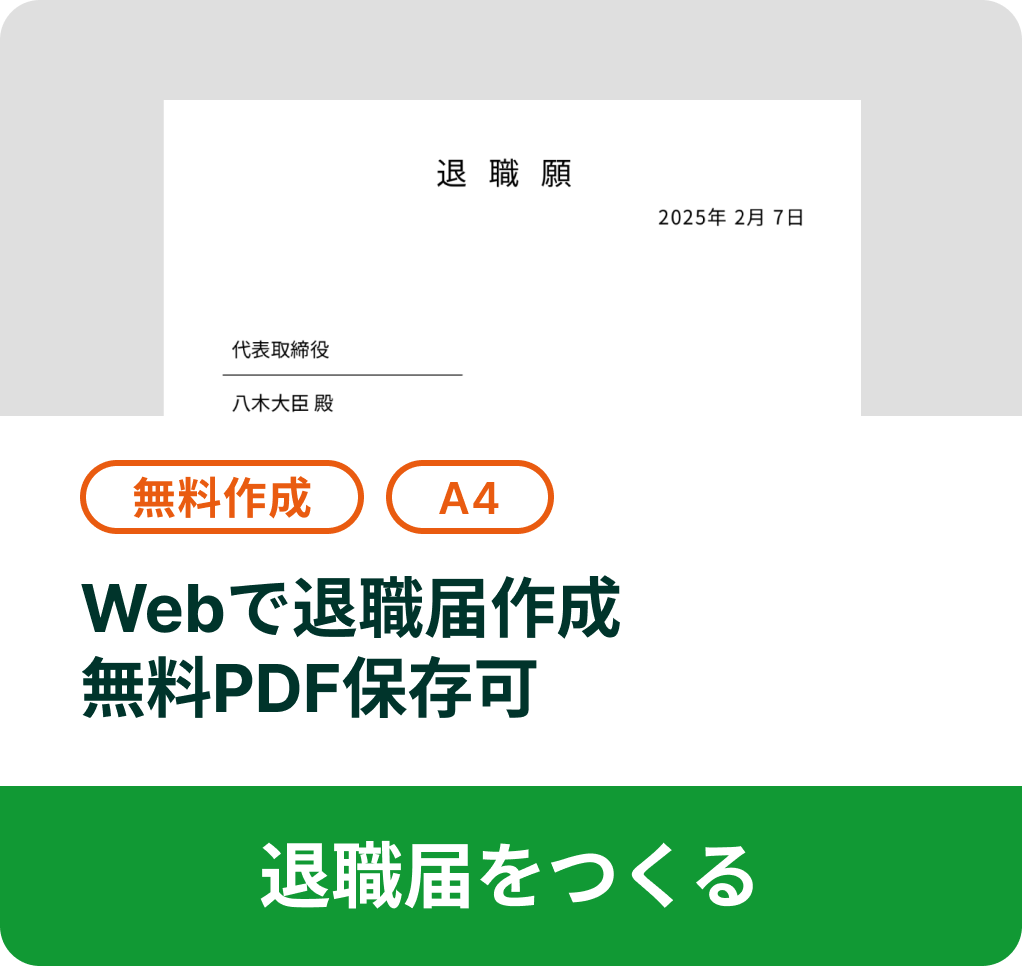

 ノウハウ一覧
ノウハウ一覧